手すりの役割
「手すりの役割」は大きく分けて3つあります。
- 移動の補助
階段の昇り降りや廊下などの移動、暗いところの誘導補助など - 動作の補助
段差やトイレなどの立ち座り、浴室の出入りや扉の開閉など - 転落や転倒の防止
窓やバルコニーからの転落や転倒防止など
さらに具体的に内容を説明していきます。
移動の補助
加齢とともに筋力や関節の機能が低下するため、高齢者の多くは、2本の足を使ったすばやい歩行が困難になります。手すりにつかまることで、介助を要する状況になっても、本人の自立や共に生活する方々の暮らしを支援する役割を持っています。
動作の補助
椅子やベッドから起き上がったり、階段を上り下りしたりといった上下移動の動作は、足腰が弱っている高齢者に大きな負担を強います。手すりにつかまって体を支えることで、一連の動作を行うときにかかる体への負担が軽くなります。
転落や転倒の防止
人は歳をとって高齢になると、視力・筋力の衰えや、運動神経の働きの低下でちょっとした気の緩みが身体のバランスを崩すことになります。衝撃の度合いや打ちどころによっては、骨折をしたり、後遺症が残ったりするおそれもあります。手すりは、高齢者の怪我を防ぐという役割を果たします。
手すりは予防にも役立ちます
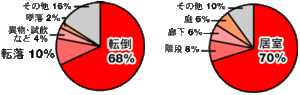
東京消防庁の統計で、家庭内で発生した不慮の救急事故のため救急車を呼んだ人のうち全体の約45%が「転倒」、約10%が「転落」でした。65歳以上の高齢者で検討したところ、家庭内事故の統計では実に約7割は「転倒」が原因でした。事故の発生場所は家の中の居室が全体の約7割、階段、廊下、庭などが転倒・転落場所となっています。
手すりに求められる役割は転倒を防ぎ、歩行や動作を円滑にし快適な日常生活を支えることにあります。予防的観点からも手すりの取り付けを検討されるケースも増えてきています。
手すりの種類と金額
介護保険を使った住宅改修をするときに検討される手すりは歩行をサポートする「移動補助」の手すりと立ち座りや姿勢をサポートする「動作補助」の手すりが大半です。移動補助の手すりはI型と呼ばれるまっすぐで長尺のもの、動作補助の手すりはトイレの横に囲むように設置されたL型のものが想像しやすいかもしれません。
手すりの種類や取付場所、長さによって金額は変動しますがここではいくつかの代表的な手すりを紹介して金額をご案内します。
木製 I型手すり

手すり 60cm ¥3,000-
取付金具(エンドホルダー)2個 ¥1,600×2
取付工事費 ¥8,000
合計 ¥14,200-(税別)
木製 L型手すり

手すり 60cm+60cm ¥3,000-
取付金具(エンドホルダー)2個 ¥1,600×2
(コーナーホルダー)1個 ¥2,800×1
取付工事費 ¥12,000
合計 ¥21,000-(税別)
木製 L型手すり+補強板

手すり 60cm+60cm ¥3,000-
取付金具(エンドホルダー)2個 ¥1,600×2
(コーナーホルダー)1個 ¥2,800×1
補強板 30cm+80cm ¥3,200-
木口化粧材 2セット ¥1,700×2
取付工事費 ¥15,000
合計 ¥30,600-(税別)
上記の金額は単体での金額です。
複数箇所ある場合は工事費の単価がお安くご提供できますのでご相談ください。
※手すりを取り付ける際は壁下地の調査が必要です。
手すりはホームセンターにも既製品が売り出されているようにDIYで簡単に取り付けられそうではありますが、取り付け場所を適切な場所に施工しないと握って力をかけた時に壁ごと崩れてしまう恐れがあるため(上記にも補強板をいれた例があります)、一度専門業者に相談することをおすすめいたします。
介護保険での住宅改修を検討する際には、ぜひ一度えにしにご相談ください。経験豊富なプロが適切な工事内容をご提案します!


